皆様、こんにちは!!
ラッコ店長です。
奈良県
奈良県に入りました。
なんと!!
南都銀行さんです。
強烈な親しみを感じます。


平城宮跡
今回のツーリングの大目的である、平城宮跡に到着しました。
あまりの壮大さ、美しさに、映画のセットか何かかと錯覚してしまうほどです。
素晴らしいです。

飽きることなく、夜まで拝見しました。


平城宮付近の公園で野営しました。
明けて次の日、少し平城宮付近を探索します。
内裏跡です。
素晴らしい。。。

今は草原となっていますが、かつてはここに都があったかと思うと、時の流れの不思議さに、感激してしまうのです。


郡山 地名の由来
平城宮周辺の資料館を拝見したかったものの、まだ早朝7時で、開館まで時間があるため、先に他の場所をめぐることにしました。
大和郡山城(やまとこおりやまじょう)です。
単に郡山城とも言いますが、福島県の郡山と区別するために、大和(現在の奈良県に相当する地域)と冠することもあります。
なお、郡山(こおりやま)という地名の由来について、古代日本、7世紀から10世紀ごろの律令制では、「郡」という行政区画がありました。
「郡」を取りまとめる役所が郡衙(ぐんが)です。
郡衙は役所でありましたが、税収を管理する倉庫があったため、警備施設、軍事施設も備えていたと思われます。
ゆえに警備、防衛の容易な丘、山に位置することもあった、と推察します。
そのため、郡衙のある山、ということで、郡山という地名が後世に伝えられた、と推察します。
かなり一般的な命名法であるため、郡山という地名、郡山城というお城は全国にいくつもあるのです。
郡山 (仙台市) – 宮城県仙台市太白区にある町名。
郡山 (白石市) – 宮城県白石市にある町名。
郡山 (羽後町) – 秋田県雄勝郡羽後町にある町名。
郡山 (酒田市) – 山形県酒田市にある町名。
郡山 (東根市) – 山形県東根市にある町名。
郡山 (南陽市) – 山形県南陽市にある町名。
郡山 (双葉町) – 福島県双葉郡双葉町にある町名。
郡山 (茨木市) – 大阪府茨木市にある町名。
郡山城 (陸奥国紫波郡) – 岩手県(陸奥国)にあった城。別名・高水寺城。
郡山城 (陸奥国安積郡) – 福島県(陸奥国)にあった城。
郡山城 (大和国) – 奈良県(大和国)にあった城。
郡山城 (摂津国) – 大阪府(摂津国)にあった城。
郡山城 (石見国) – 島根県(石見国)にあった城。
吉田郡山城 – 広島県(安芸国)にあった城。
郡山城 (薩摩国) – 鹿児島県(薩摩国)にあった城。
引用 wikipedida

大和郡山城
大和郡山城は戦国時代末期、筒井順慶さんの居城となりました。
順慶さんは本能寺の変の後、明智光秀さんの協力要請を断り、じっと情勢を伺っておりました。
その後、明智さんが無念にも山崎の戦いで羽柴秀吉さんに敗れ、順慶さんは秀吉さんに臣従することになります。
さらに時は移り、大和郡山城は秀吉さんの弟の羽柴秀長さんの居城となりました。
天下人、秀吉さんの弟の城、ということで、お城は大改修され、今でも立派な石垣が残っています。

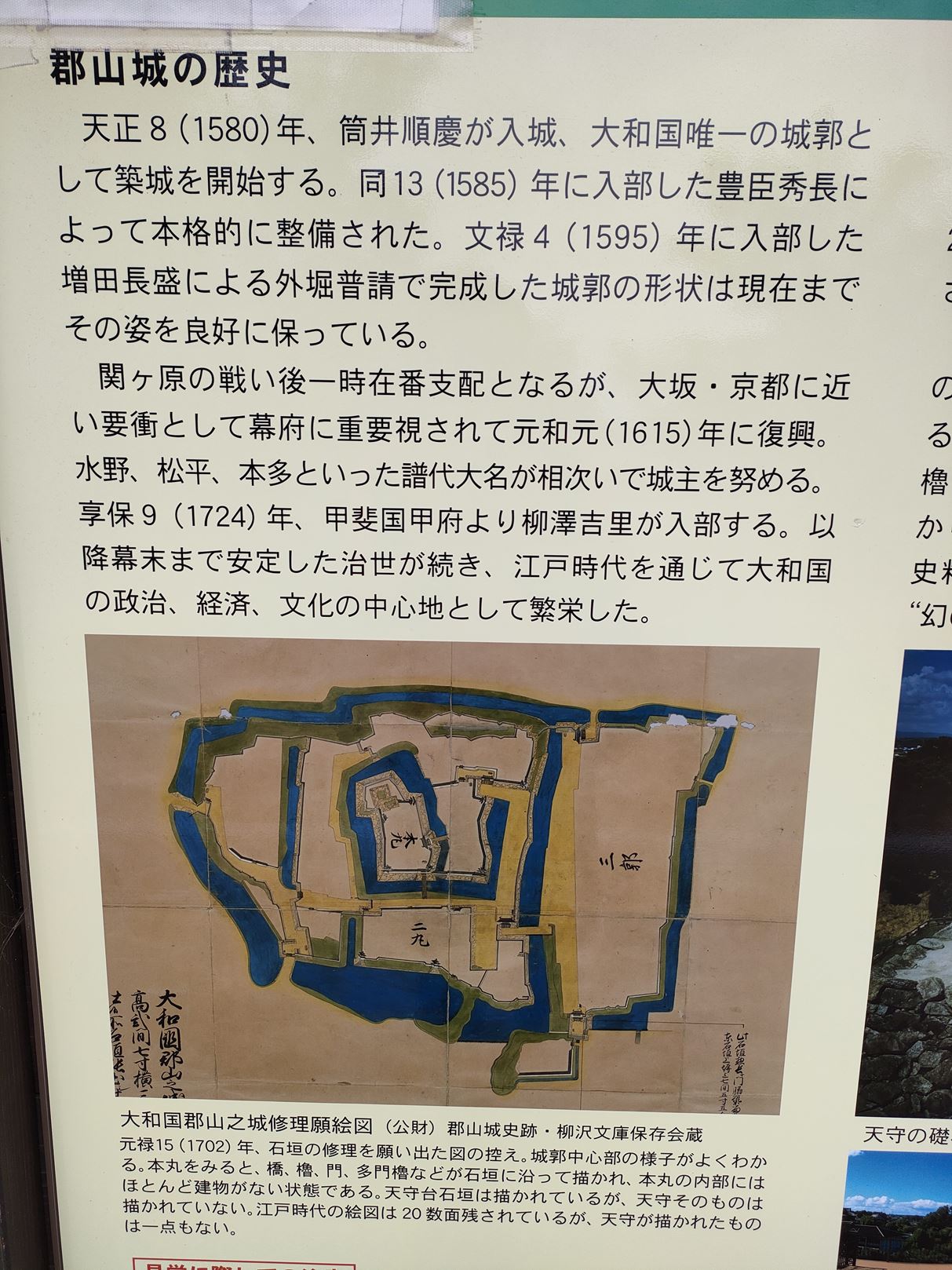
転用石 さかさ地蔵
織豊政権の城郭には、しばしば転用石という石垣が見受けられます。
石仏、宝塔、果ては墓石などを石垣の素材として使う、という手法です。
その理由は、手近な石材を使って工期を短縮させるため、寺院仏閣を威圧して支配下におさめるため、神仏の加護を受けるため、といった説がありますが、はっきりとした理由はわかりません。
しかし、単に素材として用いるのであれば、石垣の奥に配置しても良いところ、転用石はこれみよがしに目立つ場所に使われることが多く、何らかのアピールをしたかったことは明らかです。
大和郡山城にも、転用石、さかさ地蔵さんがいらっしゃいます。
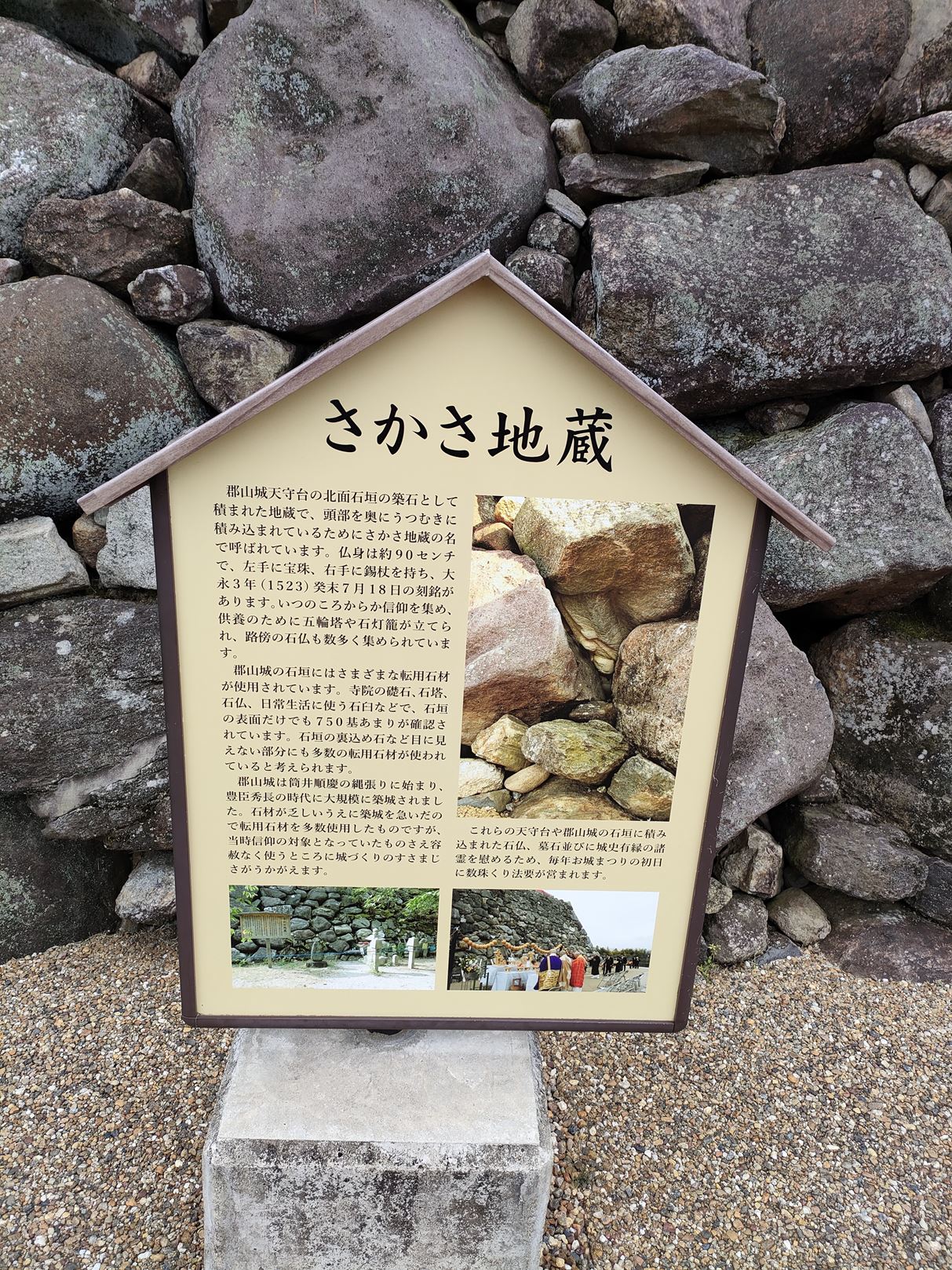

素晴らしい。
大和郡山城。
堪能しました。



本日はこのあたりで宜しいと存じます。
それでは、皆様、次回お会いするときまで、ごきげんようです!!
以上、ラッコ店長こと、奈須野でした。



コメント